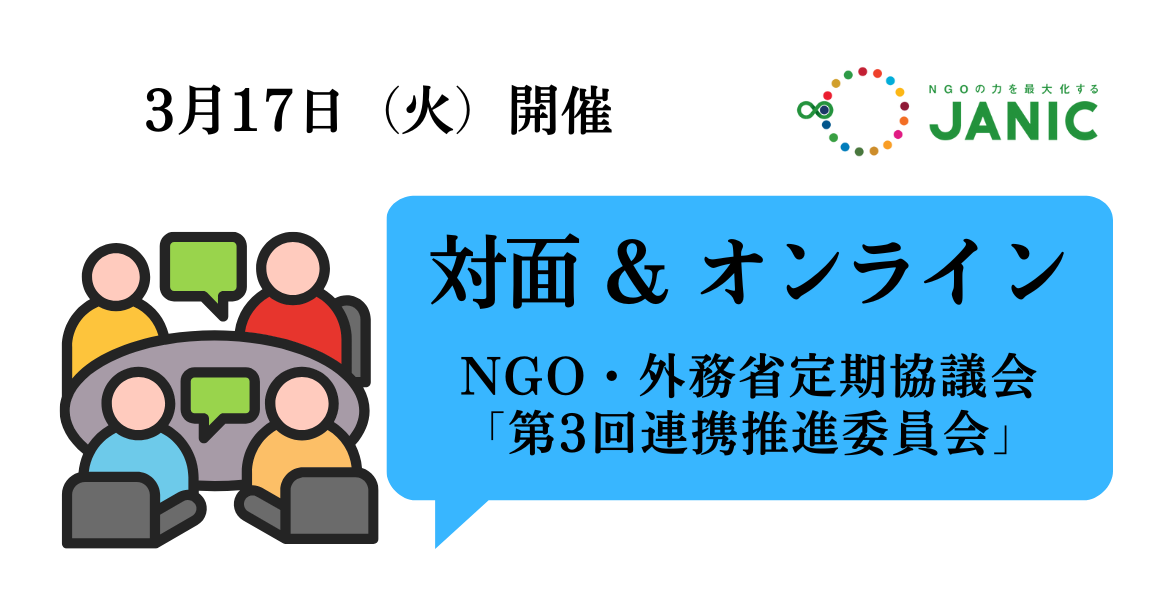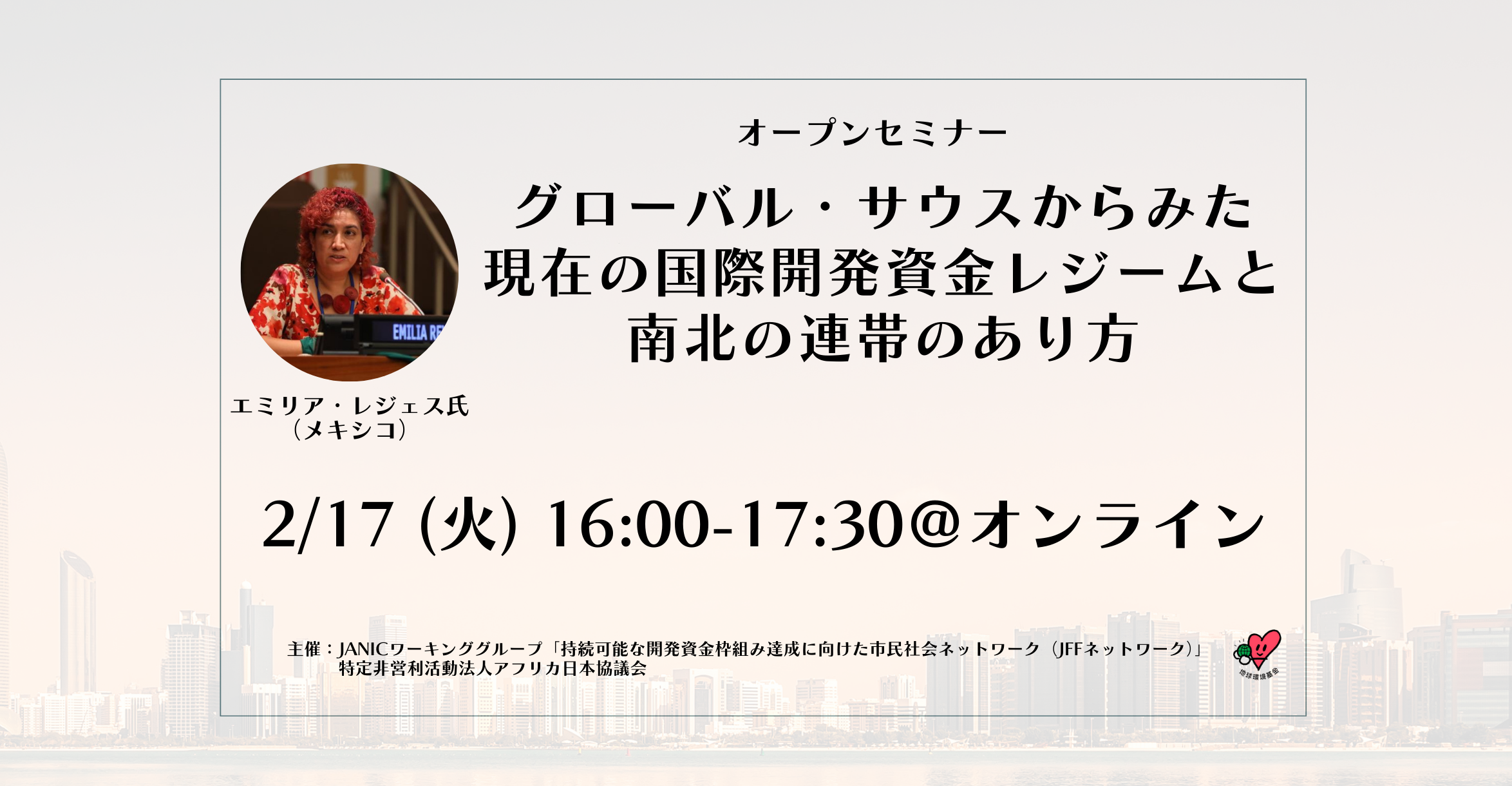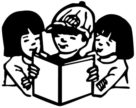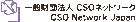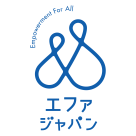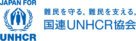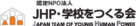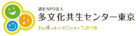- TOP
- THINK Lobby
- 【活動報告】第4回開発資金国際会議(FfD4)に向けた政策提言
【活動報告】第4回開発資金国際会議(FfD4)に向けた政策提言
THINK Lobbyライブラリー, おすすめ記事, 提言 2025.05.20
JANICでは、正会員団体であるアフリカ日本協議会、グリーンピース・ジャパンとともに、2024年度に「開発・気候資金アドボカシープロジェクト」を開始し、「持続可能な開発資金枠組み達成に向けた市民社会ネットワーク」を運営しています。同プロジェクトは、2025年度よりJANICワーキンググループとして活動しています。
このたび、同プロジェクトの共同実施団体およびアドバイザー団体とともに、本年6月30日から7月3日までスペイン・セビリアで開催される第4回開発資金国際会議(FfD4)に向けた政策提言書を発表しました。FfD4には同プロジェクトからも現地参加予定です。
PDF版のダウンロードはこちら。
外務省地球規模課題審議官組織 中村亮 地球規模課題審議官
安藤重実 地球規模総括課長
第4回開発資金国際会議(FfD4)に向けた政策提言
2025年5月20日
開発・気候資金アドボカシープロジェクト
共同実施団体:アフリカ日本協議会
国際協力NGOセンター
アドバイザー団体:アジア太平洋資料センター
グリーンピース・ジャパン
グローバル連帯税フォーラム
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
ワールド・ビジョン・ジャパン
2025年6月30日から7月3日までスペイン・セビリアにて開催される第4回開発資金国際会議(The 4th International Conference on Financing for Development、以下、FfD4)に向けて、本プロジェクトの共同実施団体およびアドバイザーは以下の提言を行います。なお、本提言は必ずしもすべての団体の見解を反映しているわけではありません。
1. 原則
FfD4は、国連加盟国が合意した持続可能な開発目標(SDGs)を含む2030アジェンダの達成期限まで残り5年となるタイミングで開催されます。
国際社会は自国優先主義の潮流が席巻しつつあるように見えますが、一国だけでは解決できない複合的危機の中で、多国間でルールを形成し、それを尊重することが、一国主義的な潮流を克服する上でも重要になっています。また、グローバルサウスの国々が経済力・政治力を高める中で、これまでのグローバルノース主導の国際秩序は揺らいでおり、グローバルサウス諸国が公正かつ対等に参画する形で、新たな国際秩序を形成していくことも重要です。現代の開発や環境をめぐる多国間交渉で見られる厳しい南北対立は、過去の不公正な歴史の清算という観点からみれば必然的なものでもあります。日本は、そのおかれた地政学的な状況に鑑みても、自国優先主義に偏することなく、多国間主義を堅持し、グローバルサウス諸国の対等な参加に基づく、より公正で調和的な新たな国際秩序の形成に向けて対話によるルール形成に主導権を発揮することが、その国益にもかなうと考えます。開発資金会議プロセスは、その重要な柱の一つであり、日本として、国際益と国益の双方をにらみながら、粘り強い対話によって克服していくことが必要です。
私たちは、この国際状況にあっても、「自発的国家レビュー」(VNR)にあたって日本政府が示している「ぶれずにSDGs達成を目指して取り組んでいく」「誰も取り残さない、誰もがイノベーションの担い手になりうる日本・世界を」という決意を強く支持します。FfD4は、世界全体でSDGsを達成することをめざし、資金ギャップを埋め、国際財政構造をより公正なものにすることを目的とした、多国間の協力の仕組みやルール作りを目指すものです。日本政府には、ぜひとも交渉にて、グローバルサウス諸国の主張を踏まえてリーダーシップを発揮し、成果を出すべく尽力していただけると幸いです。
特に、これまで開発資金や債務問題などを主要に扱ってきたいくつかの機構や枠組みは、歴史的に先進国が主導権を握る形で設置・運営されているのが現状ですが、国連開発資金会議プロセスは、国連加盟国が対等な立場で参加し、また、市民社会やその他のステークホルダーも意見を表明できる、より民主的なフォーラムとなっています。私たち市民社会は、この点で、開発資金や債務問題等の多国間での多国間の交渉やルール作りについては、この会議プロセスを含む国連の枠組みが中心になるべきだと考えています。
私たち日本のNGOは、グローバル・サウス(南側)諸国の市民社会との連帯のもとに活動を行っています。私たちは日本政府に対して、公平・平等・持続可能性といった観点を踏まえ、グローバル・サウス諸国の主張を聞き、成果に反映させることを強く要望します。開発途上国の経済・社会状況が改善することは、日本が進める「人間の安全保障」の達成により近づくと確信します。
2. 開発資金
世界経済危機以降、途上国への投資や巨大新興国の資源需要の伸びなどを要因として好景気となった途上国は、経済開発に多額の資金が投入され、これらの国々も債券を発行して経済開発のための資金を確保していきました。ところが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機と、その後のインフレ・物価高、さらにこれを抑制するための利上げなどが重なり、これらの国々は債務危機に陥り、債務不履行を宣言する国も多く出現しました。現在、これら債務危機への取り組みがパリ・クラブ等を中心になされているものの、様々な困難のために進まず、これらの国々の多くは債務返済のために教育や医療、気候変動対策などに十分な資金を回せない状況となっています。
同時に、SDGs達成に向けた最も大きな課題の一つが開発資金ギャップであり、SDGs達成のために必要とされる費用は、以前は年間2.5兆米ドル程度であったところ、COVID-19パンデミックを経て現在は年間4兆米ドルと大きく増加しています。
開発資金について、第一義的に先進各国によるODA拠出目標の達成が急務です。日本は「開発途上国に対するODAをGNI比0.7%にする」という目標に対し、2022年は0.39%、2023年は0.44%(2023年)と増加したものの、2024年は再び0.39%に戻り、DACメンバーの中では第13位と、平均よりは高いものの目標にはいまだ到達していないため、2030年までに0.7%に達する道筋を示すことが求められます。また「少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与する」という目標に対し、最新の数値は0.12%であり、この達成も求められます。さらに、ODAの増加分の多くは借款が占め、貧困対策や感染症対策に効果的な贈与(グラント)は有意に増加していないところ、グラントの大幅な増加や、DAC定義によるODAのアンタイド化を進めるべきです。
この点について、2025年3月10日に発表されたFfD4の成果文書ファーストドラフト(以下、ファーストドラフト)では、
31. 国際開発協力の量を増やし、配分を強化するために(原文:To increase volumes and enhance allocation of international development cooperation)
政府開発援助(Official development assistance)
と記載されています。0.7%目標および0.2%目標を達成するための具体的かつ拘束力のあるタイムフレームを設けている国もあり、「我々は、[…]他の国々にも同じことを求める」とありますので、日本政府も、期限を区切ったODAの増額目標を打ち出すべきです。
3. 気候資金・環境アジェンダ
国際的な気候資金の不足が叫ばれる中、気候資金の拡充に向けた議論が気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate Change、以下、UNFCCC)を中心に行われてます。一方、気候資金の不足の根本的な原因は、UNFCCCの範囲に含まれていない根本的な問題である、国際資金構造(IFA)の中での不平等な仕組みにあり、その解決なくしては、気候変動課題の解決にはありえません。そのため、国際資金構造における途上国の代表制の不在を解消することが必要です。
国内資源動員(特にパラ22)に関しては、財政ルール及び政策全体を通して、環境及び気候保護の要請を公平な方法で主流化することを奨励すべきです。国際課税ルールは、国連租税枠組条約に向けた交渉の一環として、経済、社会、環境の3つの側面における持続可能な開発の達成に、均衡のとれた統合的な形で貢献すべきです。環境に有害な補助金は、開発途上国及び影響を受ける人々やコミュニティの具体的なニーズと状況を十分に考慮し、段階的に廃止されるようすべきです。一方、環境汚染を行う多国籍企業に対しては、世界的な利潤への追加税という形で連帯税を課し、UNFCCC及び生物多様性条約に基づくグローバルな資金調達義務に充当すべきです。
パラ34(a)では、UNFCCCの目的のみが言及され、原則について触れられていません。確かに時代は以前とは異なったものになっているものの、依然として歴史的に責任がある国の排出量は、非常にわずかな一部の発展途上国を除いて途上国のそれよりも圧倒的に多いのが現状です。「共通だが差異ある責任」(common but differentiated responsibilities / CBDR)を含めて、バランスのとれた表現にすることが求められます。
パラ34(d)に記述されている「ODAと気候変動資金について報告する際の一貫性と透明性を強化し、開発と気候に関する資金のインパクトをより適切に測定するため、総会の後援の下、政府間作業部会を設置するという提案を維持する」という条項を支持し、合意に含めてください。特に、気候資金として計上されているODAには、気候変動対策にほとんど貢献しないものも含まれていたりするなど、その計算方法には問題があります。透明性を向上させるべきです。
パラ34(h)の記載は曖昧かつ、民間市場メカニズムに偏重しています。ここでは、開発途上国に対する公的気候資金の提供におけるUNFCCCの資金メカニズムの中心性を強調し、これらから拠出される年間合計金額を2022年の水準から2030年までに3倍にすることにコミットして下さい。
貿易に関するパラ39では、デユー・ディリジェンス(Due Deligence、以下、DD)について言及があるものの、先住民や地域コミュニティに対する自決権の尊重や、環境保護についての言及がまったく不十分です。DDについては、「人権DD」と「環境DD」のように明記するとともに、その土地を所有したり、そこにすむ人々の自決権を尊重することを明記すべきです。
4. 国内資源動員・国際課税
国内資源動員の観点から国際協調による税の衡平性と富の再分配が求められる中、2024年11月、国連租税枠組条約の骨子案は125か国の圧倒的多数をもって採択されました。しかし、日本は税制に関する広範なコンセンサスが反映されていないことなどを理由として、反対票を投じています。この点について、ファーストドラフトでは、
23. 国際租税協力を強化し、国際租税規則がすべての国、特に発展途上国の多様なニーズ、優先事項、能力に対応できるようにする。(原文:To strengthen international tax cooperation and to ensure that international tax rules respond to the diverse needs, priorities, and capacities of all countries, especially developing countries:)
と記載されています。また、国連租税枠組条約の交渉に建設的に関わることも表明されています。公平な税制を確立するために、日本政府はこのファーストドラフトによる提案にある通り、国連租税枠組条約交渉に関して各国との交渉を続けるなど、積極的な関与が求められます。
開発に関する追加的資金の観点からは、航空券連帯税や金融取引税などの国際連帯税により、国際的に公的資金を捻出し、社会課題に投資することが極めて重要です。2020年の「SDGsの達成のための新たな資金を考える有識者懇談会」では、航空券税に関しては「国際航空事業が正常化した段階で再考すべき」とされましたが、その後も具体化に至っていません。世界の富の配分の逆進性が高まり、貧困・格差が加速している現在、所得税や法人税の累進化を強め、税と社会保障による所得再分配機能を上げる必要があります。
「開発資金が大きく不足している現状で、これに対応しギャップを埋めるという観点からは、国際開発金融機関(MDBs)の改革、迅速な債務救済を行い重債務状況にある国を返済負担から解放すること、また、途上国の多くが重債務・気候危機など複合的危機にあることを踏まえ、これらを克服するために、今一度、SDR(特別引出権)の再配分を行い、その多くを低所得国や下位中所得国に再分配することによって、これらの国々において十分な資金流動性を確保し、資金アクセスの向上、必要な開発資金や気候資金の確保を実現することが必要です(詳細は、次節「5.債務持続可能性、国際財政構造の変革」参照)。
OECDで国際課税への合意はなされましたが、収益構造のグローバル化により、各国の税源が浸食され、また、グローバルな利益移転により超富裕層らが各国の徴税を逃れて資産を蓄積するという現象はいまだ改革されていません。その中で、グローバルに利益を得る超富裕層の資産は膨れ上がり、2024年現在、世界トップ10位の資産家の資産合計額(240兆円)は世界のODA総額(34兆円)の7倍に達しています。一方で、先進国を含め、各国は本来、各国の社会・経済開発や気候変動対策、債務の解消などに活用できるはずの公的資金をみすみす喪失する状況にあります。こうした問題を解決するには、グローバルな税源浸食や利益移転の結果として巨額な資産を築いている超富裕層への適切な課税制度は不可欠です。これは、国際課税と各国での富裕層課税の双方によって達成される必要があります。
この点について、ファーストドラフトでは、
22. 各国が必要な資源を確保し、それが透明性をもって持続可能な開発に沿った形で集められ、使われるようにする。(原文:To ensure that countries have the necessary resources, and that they are collected and spent transparently and in alignment with sustainable development:)
財政制度と持続可能な開発との整合性(Alignment of fiscal systems with sustainable development)
e) […] 我々はまた、国家主権を尊重しつつ、国際協力に支えられ、累進的な税制と富裕層への課税を促進・強化する。(We will also promote and strengthen progressive tax systems and the taxation of high-net-worth individuals, supported by international cooperation, while respecting national sovereignty.)
と記載されています。
しかし、日本政府が2025年の所得分から適用している「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置」については、「税負担の公平性の観点」からのみ導入されており、気候変動や貧困・格差対策などの地球規模課題に使われるわけではありません。グローバル・サウス諸国が求める地球規模課題への対処にも、これらの税収が使われるべきです。
5. 債務持続可能性、国際財政構造の変革
多くの国が深刻な債務危機に陥っており、対外債務の支払額は過去30年間で最高水準に達しています。FfD4において、現在の債務危機を公正・迅速かつ有意義な方法で解決し、透明性と責任ある貸借ルールを通じて将来の危機を防止するような財政構造を構築することが不可欠です。
この点で、ファーストドラフトでは、
43.[…]国連において政府間プロセスを開始し、債務構造のギャップを埋めるとともに、多国間ソブリン債務メカニズムを含みつつ、これに限定されない、債務の持続可能性に対処するための選択肢を模索する。(原文: […] we will initiate an intergovernmental process at the United Nations, with a view to closing gaps in the debt architecture and exploring options to address debt sustainability, including but not limited to a multilateral sovereign debt mechanism.)
と記述されており、これを歓迎します。
これらは、短・中期的な対処療法では解決できない構造的な課題であり、資金拠出の意思決定や実施をめぐる不平等な制度を改革する必要があります。IMF・世界銀行、OECDなど、主要な経済先進国が意思決定の中心を占め、開発資金や気候資金の受け手である途上国の意見が反映されない仕組みは是正されなければなりません。
例えば、2024年8月24日と25日に日本で開催されたアフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合共同コミュニケにおいて、「我々は、国内外の資金源を動員する観点から、税制システム改革について協力することの重要性を認識した。我々は、アフリカ開発銀行への特別引出権(Special Drawing Rights、以下、SDR)の分配、アフリカの持続可能で安価かつ衡平な資金へのアクセスの促進及び再発する対外債務危機への対応を含め、AUアジェンダ2063及び持続可能な開発目標のためのアジェンダ2030を加速する投資のための資本を動員する緊急性を認識した」と言及されています。アフリカ連合やアフリカ諸国は、2023年9月にも「アフリカ気候サミット」を開催し、気候危機に対処するためのSDRの新たな配分などを含め、必要な資金確保を積極的に主張しています。日本を含む先進国はこれを支持し、実現に向けて取り組む必要があります。
SDRの配分および途上国への分配については、IMF・世界銀行でも議論が進んでおり、脆弱国の財政再建や気候適応資金への活用が期待されています。日本政府は、これまでもG7諸国の中でも積極的にSDRの活用などに取り組み、アフリカ開発銀行を通じたSDRの分配に積極的に取り組み、他のG7諸国にも同様の動きを呼びかける必要があります。
特に、今日の国際的な危機にあって、日本政府はSDRに関して、次のような政策を国際的に呼びかけるべきです。
日本政府は流動性と準備資産を十分に有しているので、これまでの40%のチャネリングに加えて、残りの60%(238億ドル相当)をチャネリングすることが可能です。
(以上)
本件に関する問い合わせ先:
開発・気候資金アドボカシープロジェクト 共同実施団体 国際協力NGOセンター
03-6435-2945 / janic-advocacy@janic.org(担当:堀内、柴田)
JANIC正会員団体
FOLLOW US