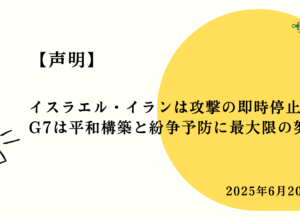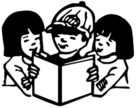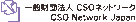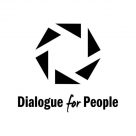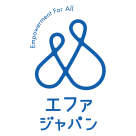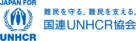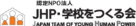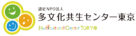JANIC / 国際協力NGOセンターは、NGOの力を最大化することで世界の社会課題解決の促進を目指す、ネットワークNGOです。
JANICからのお知らせ
NGOインフォメーション
FROM | ACE (エース)
FROM | ウォーターエイドジャパン
JUL.07.2025
【参加者募集】2025年7月29日(火)・30日(水)実施:NGO等向け基礎からはじめる国際協力事業研修 (Bモニタリング・評価編)
JICA - 国際協力機構
JUL.07.2025
FROM | JICA - 国際協力機構
THINK Lobby
JANIC正会員団体
FOLLOW US

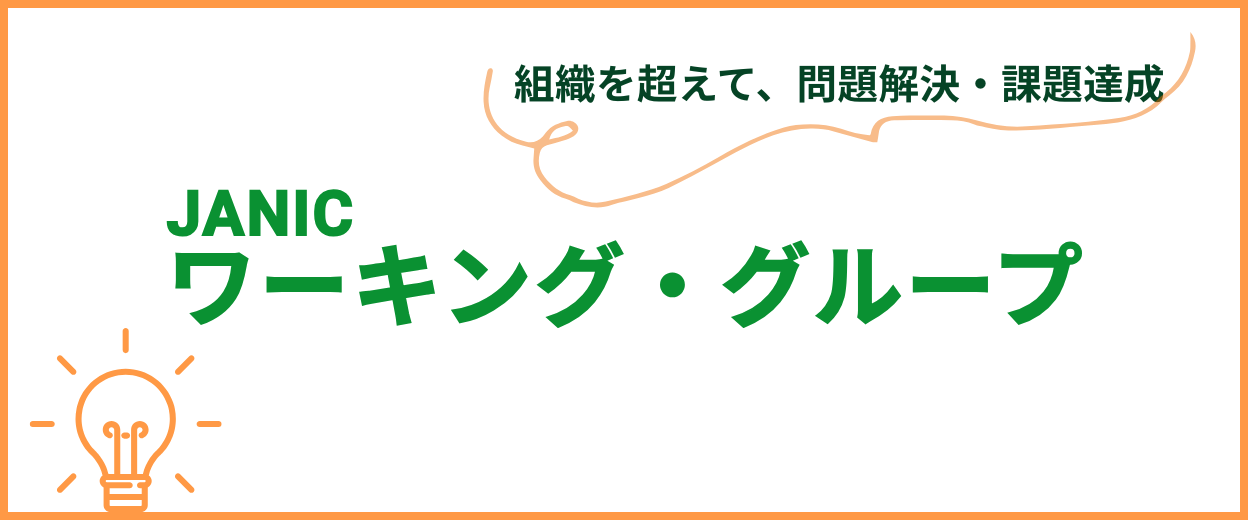







 JANIC学生アイデアコンテスト2025エントリー受付開始!
JANIC学生アイデアコンテスト2025エントリー受付開始!